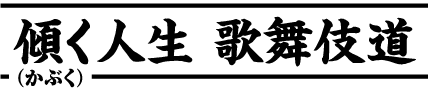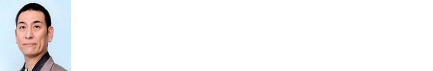Topics
勝新流ギャンブル、セックス、女の口説き方 ~
最後の「弟子」が見た勝新太郎・男の生きざま
■傾く人生 歌舞伎道 銀座・成田屋のトピックス

妻・中村玉緒との貴重なツーショット(結婚は62年、写真は65年ごろ)
ぼくは、勝新太郎の最後の「弟子」だった――。晩年の勝新太郎と濃密な時間を過ごしたノンフィクションライターの田崎健太氏が、勝新の駆け抜けた人生を著した『偶然完全 勝新太郎伝』。勝新の豪快エピソードが詰まった部分を特別公開する!
勝流「女の口説き方」
『週刊ポスト』で、勝新太郎による人生相談の連載担当になった筆者は、初対面から彼の放つ魅力に惹きつけられる。そして、勝に振り回されるとんでもない日々が始まった――。
次の取材は、勝プロで話を聞くことになっていた。連載は始まっておらずまだ質問は来ていない。そこで事前取材としてぼくが聞きたいことを、ファックスで送っていた。勝の部屋に入ると、老眼鏡を掛けてその紙を読み耽っていた。
「粋な遊びとは何かって聞かれてもね」
勝は顔を上げた。粋な遊びを教えて下さいという質問を入れておいたのだ。
「綺麗な女の子を見る度に、この子は今夜付き合ってくれるかなぁなんて考えていたら、遊びが裕福にならない。なんというか、遊びっていうのはキャッチボールみたいなものだね。
今日パーティがあるとする。その前に軽くお腹に入れていくだろ? それと同じで、遊びに行く前に、一遍せんずりやって、自分で出すものを出すんだよ。
銀座のクラブであれ、祇園町のお座敷であれ、自分の隣に座ってくれた女の人がどれだけ楽しんでくれるか。その人たちに好きな飲み物を頼んであげて、楽しませる。
金がなくちゃ遊べないけど、株で儲けたとか地上げで儲けたとか、金があるから遊べるもんでもない。粋がないとね。粋という、粋だけじゃなくて、心意気の〝いき〟でもある」
遊びと言えばこんな話がある、と話し始めた。
「昔、ある長唄の師匠がいた。所帯持ちの人だったんだけれど、芸者のことが好きになって口説いた。そうしたらその芸者が、おっしょさん、いいわよ、浮気しても、って言ってくれた。ある夜、待ち合わせて食事をしようということになった。
ところが、その師匠は懐が寂しくてね。そこで一人分を浮かそうと考えた。他の弟子たちがステーキを食べたいって言うから、帝国ホテルで食べてくるので先に食べておいてくれって言ったんだ。彼女が待っている近くをうろうろして、チャーシュー麺か何かを食べてから、店に行った。この芸者というのは酒が強くてね。
がばがば飲まされちゃって、その内、悪酔いしちゃったんだよ」
上半身を揺らせて酔った振りをした。
「大丈夫、大丈夫っていいながら、戻してしまった。みなが駆け寄ると、戻したものの中にあるのはラーメンだけなんだよ。師匠はそれに気がついて、必死で〝もうすぐステーキが出てくるから〟って」
勝の苦しそうな表情にぼくは吹き出してしまった。
お前はC級、俺もC級
自分が話すだけでなく、ぼくのことも聞きたがった。
勝は週刊誌にはいつも目を通しており、激しく部数を競っていることを知っていた。ぼくは他の週刊誌、特に週刊文春に苦労させられたことを話した。ある人物に取材を申し込んで、こちらは完全に断られているのに、翌週の週刊文春に独占手記が載っていたこともあった。
「ぼくも手紙を置いてきたりと工夫しているんですけれど、文春の方に出たがるんですよね」
「どうしてなんだ?」
「文春の記者の書く手紙が上手いという話は聞きます。でも、それ以上に文春と言えば、文芸の印象もあるし、イメージがいいからじゃないですか?」
「文春はA級ということか?」
「A級かどうかは分かりませんが、ポストより印象はいいでしょうね」
勝は、どんと机を叩いた。
「だから、俺はポストで連載をするんだよ。俺の映画はC級だ。ポストもC級。でも、A級の黒澤の映画よりも、お客さんが喜んでくれるのは、C級の俺の映画だ。C級だからいいんだよ」
週刊ポストは、ヘアヌード写真で部数を伸ばしていると文春の人間たちから揶揄されていた。もちろん、そうした面もあったろうが、記事の内容でも負けてはいない自信はあった。ただ、勝にC級と言われると、それでもいい気がした。
映画界での勝の噂を聞いていた連載班の上司は、原稿を早めに仕上げ、出来れば数週間分は先行しておくようにと言った。そのため、連載班で長く仕事をしている編集プロダクションの人間が取材に同行し、原稿をまとめることになっていた。
午後から始まった取材は数時間に及び、夕方になっていた。
「私が、読者から来た質問のような形で今日の取材を原稿にします。私は次があるので今日はここで」
と編集プロダクションの男が先に引き揚げていった。ぼくはどうしようかと考えていると、勝が腰を浮かせた。
「今日、時間あるか?」
「はい」
「じゃ、飯でも行くか」
勝とぼくは、飯倉片町の交差点に近いステーキハウスに向かった。
勝新流「ギャンブルのススメ」
薄暗い店でも大きな帽子を被った勝は目立った。他の客が勝のことをひそひそと話している姿が見えた。
「一番大きな肉、レアーでな。お前も同じものでいいか?」
しばらくして鉄板に載せられた大きな肉片が出てきた。
「これが旨いんだ」
噛むと肉汁がしみ出してくる、美味しい肉だった。
半分ほど食べ終わった頃だ。勝はナイフとフォークで自分の皿にあった肉片を素早くぼくの皿に載せた。どうしたのかと顔を覗き込むと、何もなかったように話を続けた。これも食べろという意味かなと思い、全部食べることにした。
食事の後、今度は六本木の交差点に向かった。交差点から少し入ったところにナイトクラブがあった。入り口には大きな黒人が立っており、勝は親しげに手を上げて中に入った。店内には外国人ホステスがおり、カジノテーブルがあった。勝は慣れた感じで席に着くと、蝶ネクタイをしたディーラーがカードを配った。
「カモン」
勝は大きな声を出してテーブルを叩いた。ディーラーがカードをめくり、負けると、手を額に当てて悔しそうな顔をした。
──勝新じゃない?
周囲から囁く声が聞こえた。
「ワンモア」
勝が積み上げるチップは、周りとは高さが違った。大きく張る勝を見ようと、人が遠巻きに集まっていた。注目されるのを勝は楽しんでいるようだった。
まだまだ勝負は続きそうだった。昼過ぎに編集部を出てから、一度も戻っていない。そろそろ戻りますと、ぼくは勝の耳元で囁いた。するとそうかと気のなさそうな返事をして、勝はポケットに手を入れた。
「お前、タクシー代はあるか?」
「大丈夫ですよ」
ぼくは慌てて手を振った。
後で、ぼくが引き揚げてから半時間もしないうちに勝は帰ったと聞いた。自分と仕事を始めたばかりのぼくを楽しませようとして、わざと大きな声で賭ける姿を見せたのだ。
思い返してみれば、ステーキハウスでも、勝は一番大きなステーキを食べているという印象を他の客に与えようとしていたのかもしれない。常に誰かから見られていることを意識している人だった。
勝新のテープレコーダーの中身
翌日、編集プロダクションから原稿が送られてきた。週刊誌らしい軽妙な文体で、そつなくまとまっていた。上司に見せると「面白いじゃないか」と褒めた。しかし、こうした原稿を勝が一番嫌がるような気がした。勝プロに送ると、すぐに常務の眞田から電話が入った。
「勝がこの原稿は気に入らないそうです。言いにくいんですが、昨日の方は外して、あなたと二人で出来ないかと勝は言っています」
上司に相談し、ぼくが原稿にまとめることになった。上司たちは内館とのやり取りを知っているので、口を挟むことはないだろう。ぼくは勝と二人で連載を進めることになったのだ。
勝は、読者の質問へ真摯に答えることにこだわった。ぼくが一緒にいない時に答えを思いつくこともあるだろう。そうした時のために、勝にテープレコーダーを渡して、答えを吹き込んでもらうことにした。
ぼくは自分が使っているのと同じソニーの無骨なテープレコーダーを勝プロに持って行った。二つを間違えるといけないと、勝の息子の雄大が気を遣って、〈TAZAKI〉と〈KATSU〉と印字したテープをそれぞれに貼り付けてくれた。
都々逸や小唄を使った、粋な口説き文句を教えてくれという質問には、こんな答えが返ってきた。
「口説き文句なんてぇものは人に教わるものじゃねぇよ。自分でオリジナル口説き文句をつくりゃあいいんだ」
節をつけて、都々逸を歌い始めた。
「夕立の ざっとふるほど 浮名は立てど ただの一度も 濡れやせぬ」
自分は沢山の女性と噂を立てられているけれど、一度だって他の女性とは寝たことはないという意味である。勝の語り口には心地よい抑揚があり、間の取り方が絶妙だった。
〈KATSU〉のカセットテープにはこんな吹き込みもあった。
「俺の入っていた聖地って言やわかるだろ? 東京の川の流れてる近くにある聖地さ。わかったかい?」
ハワイから戻り、勝が収監されていた小菅の拘置所のことだ。
「アラーの神にお願いごとをする所じゃないよ。今までの自分を自分で見て、その自分のいい所を出す場所さ。まぁ、あんないい所はないな。
ただ、部屋の鍵を外から掛けられるってぇのが、ちょっと気になったけどさ。自分の部屋なのに、自分で中から鍵を掛けられないなんてぇのがなぁ……。
うん、それでも聖地さ。
夜の九時になると部屋の電気が消えるんだ。自分で消すんじゃないよ。そんな面倒臭いことをしなくても、音楽が鳴り止むと自然に電気が消えるってぇ寸法さ。
いい所だろ?
入りたいだろ?
なかなか入れてくれねぇんだ、うん。
電気が消えて暗くなると、窓に月が出ていて、俺をじーっと見ているんだ。俺も月をじーっと見るんだ。
ハワイで見た月も、家で見た月も、月には変わりはねぇんだけれど、何か変わっているんだ。よーく見ていると、月と俺の間に鉄の格子があるんだよ。うん、運のつきってぇ奴さ」
勝新流セックス
ぼくの仕事は質問と勝の言葉をパズルのように組み合わせていくことだった。勝の言葉が持っている抑揚と間を生かそうと、ぼくは音読をしながら原稿を書いた。
書き上げた原稿をファックスで送ると、ぼくが事務所を訪ねる前に、勝は鉛筆で修正を入れていた。直しは丁寧ではあったが、中には日本語としておかしくなってしまう箇所もあった。
「勝さん、ここを直すとおかしいです」
ぼくは勝が書き込んだ部分を指さした。
すると、勝は目をかっと見開いた。
「お前、俺の直しが気に入らないっていうのかい?」
ここで引き下がるわけにはいかない。黙って勝を見つめると、彼は視線を外してふっと笑った。
「お前は、黒澤より偉いな。黒澤は俺にそんなことを言えなかったよ」
勝の表現は映像的で、文章を生業とする人間が使う言葉とは違っていた。
性行為は、勝の手に掛かるとこうなる。
「女っていうのは、男を愛してくるってぇいうと、だんだん男を包みたい、最後の一滴まで絞るようなセックスに変わってくるんだよ。淫乱でそうなってくるんじゃなくて、愛しているからそうなってくる。
ああ、もう、あたしぃ──いやっ、いーっ、いーっ。
なんてうなりだした時、中が欠伸して、洞窟になっちゃうなんてのもある。肉がぶわっと壁にくっついちゃう。サーカスのテントのドームみたいになって、オートバイでぐるぐる、ぐるぐる回る曲芸ができるぐらいの壁になっちゃって、ドームの真ん中で麻雀なんかしているような女の人もいるんだ。
そのうち、その壁がだんだんちっちゃくなっていって、巾着みたいになっちゃって、その中に入ったらもう生きて出られねぇんじゃねぇか、って変わってくる。
助平、淫乱だからじゃなく、その男を愛しているからそうなるんだ。男の命の泉の一滴まで絞りとろうとする女の本能は凄いぜ」
身ぶり手ぶりの入ったこうした話は酒を飲みながら聞いた。
勝が好んでいたのは、テキーラの入ったショットグラスを逆さまにしてグラスの底に置き、上からビールを注ぐ、サブマリンという飲み方だった。グラスを傾けると、少しずつテキーラが漏れ出てくるのだ。ビールの苦みに少し甘いテキーラが混じって口当たりがいい。
いつも勝は芝居のことを考えていた。勝の部屋ではテレビがつけっぱなしになっており、勝はリモコンを握り頻繁にチャンネルを変えた。ワイドショーに記者会見で弁明している人が出ていると、こいつを見てごらんと指さした。
楽しくて仕方がなかった
「言い訳の芝居は誰でもできる。芝居をつける必要がないんだ。言い訳の芝居が巧いだろ。こういう風にやるんだ」
勝と初対面だという緊張した人間の前で、いきなり硝子テーブルの上に白い粉を広げたことがあった。何も言わずに、ナイフを使って線状に整えると勢いよく鼻から吸い込んだ。
客の表情が固まったのを見て、「その顔を忘れちゃ駄目だよ。驚く時の顔はそうやるんだ」とにやりと笑った。そして「これはヤクじゃないよ、風邪薬だ。こうやるとよく効くんだよ」と付け加えた。
長く一緒にいると、彼の陰の部分を覗き見ることもあった。平日午後に多いテレビドラマの再放送を見ながら、「どうしてこんなのが受けるんだろうな」と呟いていた。
勝のところには、様々な仕事が持ち込まれていた。それは勝が本当にやりたいこと──腰を据えた映画やテレビドラマではなかった。勅使河原宏とのイタリアでの映画製作が、直前で中止となったことがあった。勝との仕事は予定通りに進まない。六十歳を超え、勝は映画界で扱いづらい存在となっていた。
勝は百本以上の映画に出演し、悠々と過ごしてもおかしくない実績があった。しかし、彼の中には自分はまだ表現しきっていないという焦りがあった。
「影を持っている人間だからこそ、光り輝くものが出てくる。影から出てくるそいつ独自の生き方、光に人は憧れるんだ。今は影のない役者がスターになれる。本物よりも本物によく似た偽物の方が扱いやすい。気位がないから使いやすいんだ」
ぼくはほぼ毎日、勝の自宅、もしくは事務所に行き、日が暮れると食事に出かけた。料亭のような店もあれば、トンカツ屋などもあった。高級そうな店でも庶民的な店でも勝の態度は変わらなかった。店員に優しく接し、チップを渡した。
勝は車の運転が好きで、白色のトヨタセンチュリーを自分で運転することが多かった。運転手がいる場合には、店に入るとまず「うちの運転手に何か食べるものを運んでおいてくれるかい」と頼んだ。この優しさが彼の周りから人が去っていかない理由だった。
支払いはいつも、ぼくが気がつかないうちに勝が済ませていた。あまりにそうしたことが続くので心苦しくなり、「ぼくも払います」、「取材経費を使わせてください」と言ったこともある。しかし、勝は「いいんだよ」と首を振った。
「昔、どうしても自分に支払いをさせてくれという男がいたんだ。何回も言うから仕方がないから、払ってもらったことがある。そうしたら、勝新を連れて飲ませていると金が掛かって困るって、そいつが言っているのが聞こえてきた。お前もそんな風に言いたいんじゃないだろうな」
そう言ってにっこりと笑った。
勝と一緒にいると楽しくて仕方がなかった――。
【田崎健太(たざき・けんた)】
1968年京都生まれ。早稲田大学法学部卒業後、小学館に入社。『週刊ポスト』編集部などを経て、99年に退社、ノンフィクション作家に。近著に『真説・長州力』『球童 伊良部秀輝伝』などがある。早稲田大学スポーツ産業研究所招聘研究員
引用:現代ビジネス|講談社
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/45914?page=1